ティランジアの栽培を始めて数年たちます。その間の経験を元に、私なりの栽培法を紹介したいと思います。
よい株の選び方
最近はホームセンターなどでもティランジアを扱うようになり、気軽に入手できるようになりました。しかし、お店での管理が悪く状態のよくない株が並んでいることもしばしばあります。そこで、私なりのよい株の選び方を書いてみたいと思います。
入手後のケア
専門業者や管理のよいお店で購入した場合には、そのまま育てても問題ないと思いますが、私の経験上、専門業者以外で購入した場合は水切れになっていることが多いようです。そこで、私はまずソーキング(水遣り法:後述)を行い、直射日光の当たらない風通しのよい場所で2〜3日様子を見るようにしています。
植え付けの勧め
水遣りが充分であれば棚の上に転がしておくだけでも大抵のティランジアは元気に育ってくれますが、何かに植えつけたほうがうまく育ってくれます。これは植物自体は乾いている方がよいのですが、逆に空中湿度は高いほうがティランジアにはよい環境となるからです。
水遣り後には植え付け材からも水分が供給されますので、より長時間空中湿度を維持することができます。
また、ツル植物が周りの物体を感知して弦を伸ばすように、植えつけることによって植物自体に何らかの影響があるのかもしれません。
着生法:木片などにくっつける方法です。コルク樹皮やヘゴ材、カクタススケルトン、流木などがよく用いられます。成長してくると樹形が崩れやすい茎が長く伸びるタイプのティランジアに向いているようです。
また、アレンジは自由自在ですので、センスよく作られたものはオブジェとしてもすばらしいものになります。自然の姿に最も近い栽培法といえます。
くっつける際にはボンドや針金、麻ヒモなどを用います。状態がよければ数週間で発根してがっちりくっつきますので仮止め程度の気持ちで行いましょう。
筆者がお勧めなのは、フラワーアレンジメントに使われる細い針金です。これは細くて加工がしやすい上に表面が紙でコーティングしてあるため植物を傷つけません。また色も緑や茶色で目立ちません。鉄製ですので、化学的にも銅線などのような(銅イオンは有害)植物に対する害も比較適少ないと思われます。
熱溶解式のボンドで流木などにくっつけてある商品をよく見かけますが、植物自体を傷つけてしまう可能性があるので、なれないひとにはあまりお勧めできません。どうしてもボンドでつけたい場合には、まず植物に針金などを巻きつけて、その針金にボンドをつけるようにするとうまくいきます。
着生させる場合の欠点は鉢に植え込んだ場合よりも乾燥しやすいということです。植物の状態を見て、水切れしやすいようであれば灌水の頻度を増やすか植え込み法を変えてください。
 |
| 木片に 針金で縛り付けて5ヶ月ほど経ったティランジア・イオナンタです。 茶色の根っこが木片にがっちり食い込んでいます。 この後針金をはずしましたが、しっかりとくっついていました。 |
鉢植え法:植木鉢は素焼き鉢のように水を通すものと、塗り鉢やプラスチック鉢のように水を通さないものに分けられます。それぞれに特徴がありますので、植物の性質に合わせて使い分けます。
植え込む際の用土は、軽石やバークチップ、椰子ガラチップ(ベラボン)、ミズゴケ等が適しています。
筆者は主に軽石とバークチップを用いています。ベラボンは、筆者の住んでいる地域では手に入りにくいものなので、使用経験がほとんどありません。
軽石の特性として、水を吸収しやすく排出しやすい(保水力少)、また多くの水を吸収することができる(保水量大)といえます。筆者の経験では素焼き鉢と最も相性がよいようです。素焼き鉢は鉢の表面からも水が蒸散してゆきますので、速乾性に優れ、気化熱を奪うことにより冷却効果も期待できます。毛細管現象で軽石に蓄えられた水分はは速やかに鉢から空気中に蒸散してゆきます。さらに、軽石は保水量が大きいので比較的長時間水を供給することができます。
プラ鉢などで使用すると、保水量が多いためいつまでも乾かず蒸れの原因となります。軽石+素焼き鉢の組み合わせは葉の硬い乾燥に強いタイプのティランジアに向いています。
バークチップは水を吸収しにくいかわりに排出しにくく(保水力大)、一方であまり水を蓄えてくれません(保水量小)。こちらはプラ鉢などの水を通さない鉢で使用すると、蒸れない程度の程よく湿った状態を長時間維持してくれます。トリコームの少ない水切れしやすいタイプのティランジアや高湿度を要求する坪型種、緑葉系のティランジアに適しています。
ミズゴケはランの栽培ではほぼ必須といっても過言ではありませんが、銀葉ティランジアには保湿性がよすぎるので蒸れの原因になりやすく、常に通風を確保する必要があります。また、素焼き鉢のように通水性に優れた鉢と組み合わせる必要があります。初心者にはあまりお勧めできません。
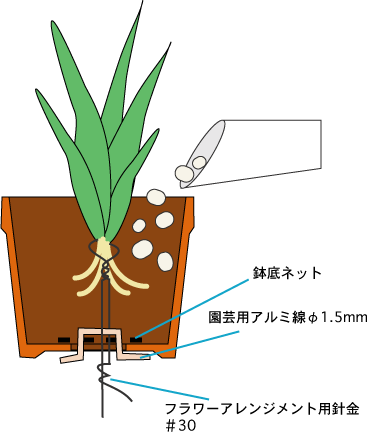 |
最後に植え込み法です。 素焼き鉢に植え込む場合をイラストにしてみました。 基本的に鉢底ネットをアルミ線でしっかり固定し、植物を針金で鉢底ネットに固定します。 手順は
イラストは一般的な植木鉢の場合ですが、プラ鉢は形状が多彩ですので、それぞれ工夫してください。 |
その他:植え付けなんて面倒だと言う方には、素焼き鉢の中にコロンと転がしておくという方法もあります。見栄えを気にしなければ、しばらく栽培しているうちに根を伸ばして勝手にくっついてしまうことも多いので最も簡単で効果的な方法ともいえます。
置き場所と環境
ティランジアはサボテンのように砂漠に生えている植物だと思っている方も多いようですが、一部の強健種を除いて、殆どが木漏れ日の当たる木陰や午前中だけ直射日光の当たるような場所に生えています。
そして、比較的涼しい環境を好む植物です。
さらに、「一般に市販されているティランジアが全て育てやすいとは限らない」ということは理解しておく必要があります。ティランジアはすぐに枯れることはないため、本来栽培が難しい高山植物的な性質を持つものもホームセンターに並んでいたりするのです。
そういった現状を踏まえた上で、押さえておく条件は二つ。日照と風通しです。
「風通しのよい、直射日光の当たらない明るい日陰」が最も適した栽培環境です。
マンション暮らしをしていた頃、我が家では主にベランダで植物を育てていました。ベランダは日当たりがよく、風通しは良いのですがその分乾燥が強いため、一般的な植物にとっては過酷な環境です。しかし、ブロメリアなどのように乾燥に強い植物達にとっては理想的な環境であることも多いのです。特に、多くのティランジアにとってベランダは理想的な環境といえます。
最低気温が10℃以上の期間(福岡市内では4月〜10月中旬)はベランダに出しっぱなしで問題ありませんが、冬の時期の置き場所をどうするかが問題になります。栽培している数が多い方は温室を設置したほうがよいでしょうし、数が少ない方は室内で管理することになると思います。
筆者の場合、マンション住まいのころは冬場はベランダに設置した小型ビニールハウスで越冬していました。温室内は小型の電気ファンヒーターで最低気温13℃に設定。水やりはだいたい一日おきに超音波加湿器を夜間に使用しているのと、週一回程度は暖かい日中にホースで水まきをしています。また、空気の流れを作るためにクリップファンを24時間回しっぱなしにしています。冬場は太陽が低くなって直射日光に照らされることも多いので遮光は約50%していました。
問題点としては、春や秋には晴天時にハウス内が40℃を越えるような状態になることです。水槽用の逆サーモを利用して換気扇制作も考えたのですが、めんどくさくなって頓挫してしまいました。結局、朝出勤時にチャックを開けて、帰宅時にしめるというパターンで落ち着きました。ビニールハウスを導入して、冬場に調子を崩す植物も少なくなり、すこぶる調子が良くなりました。また、冬場に開花する種類の失敗が無くなりました。
室内栽培の場合も、日照と通風の基本は変わらないのですが、気をつけないといけないのはエアコンの風です。エアコンから出てくる風は非常に湿度の低いある意味異常な風ですので、ティランジアには有害な場合が多いようです。直接風の当たる場所は避けましょう。
直射日光の当たらない明るい窓辺や、レースのカーテン越しに日光が当たる場所が理想的です。
また、水周りは空中湿度が高く保てますので、日照が確保できればよい置き場所になると思います。
寒い時期には蒸れの心配がありませんし、低温で植物自体の生理的な活性も低いでしょうから、通風にはあまりこだわらなくてもよいのかもしれません。むしろ乾燥しすぎに注意が必要なようです。
棚の上に裸で転がしておくよりもテラリウム用のガラス容器やザルの上など少しでも湿度の保ちやすい工夫をしたほうがよいようです。
水遣り
ティランジアは案外水が好きです。乾燥に強いのは事実ですが、長期間水を与えなくても枯れないというだけで状態よく育てるためには適切な水遣りが欠かせません。水遣りには二つの方法があります。まずひとつ目は普通の植物と同じように上からジャブジャブ水をかける方法。数が多い場合や植え込んだ場合に適しています。二つ目はソーキングといわれる方法。こちらは少数を室内栽培している場合に適しています。
注意しないといけないのはいつまでも濡れていてはいけないということです。高温時の蒸れは致命傷になることが多いので注意が必要です。半日程度で完全に乾いてしまう様な環境が理想です。
ジャブジャブ法:とにかくビショビショになるまでしっかり水を与えます。うちでは夏場は、水やりはほぼ毎日、夕方にホースでじゃぶじゃぶ水をかけています。CAM植物(主に夜間に水、二酸化炭素を吸収する植物)ですし、比較的涼しい環境を好む植物ですので、夜間の温度を下げる意味も含めてこの時間に水やりをしています。春・秋の比較的気温の低い時期には昼間の暖かい時間に水まきをすることもあります。冬場は暖かい昼間に週一回程度水をまいています。水遣りの頻度や時間は栽培環境により異なりますので、乾き具合を見て調節してください。
ソーキング:週一回程度、一晩バケツで水につけておくという方法です。室温と同じくらいの温度の水にドボンとつけておくだけです。あまり時間は気にする必要ありません。朝、水から上げたらよく水を切って直射日光の当たらない風通しのよい場所で乾かしましょう。
 |
| ↑自生地のティランジア・ジュンセア(メキシコ、オアハカ州) |
Copyright(C). Ichiro Ueno. all right reserved.